災害被災地支援

詳細については画像をクリックしてください。
全国保育士会では、平成23年3月11日の東日本大震災発生後、御園愛子顧問(当時会長)が被災地に赴き保育士を励まし、その後、執行部で支援策を検討した結果、「東日本大震災被災地保育士会支援募金(通称:スカンポ募金)」を立ち上げ、特に被害が甚大であった岩手県・宮城県・福島県の保育士会を支援することを通じて、被災した保育士を応援しました。
また、平成28年熊本地震(平成28年4月14日)の発生を受けて、他の大規模災害に対する支援にも活用できるよう、「東日本大震災被災地保育士会支援募金(通称:スカンポ募金)」の名称を「全国保育士会被災地支援スカンポ募金」に変更しました。そのうえで、あらためて全国保育士会会員に募金を呼びかけ、被災した地域の保育士会の運営を支援するとともに、子どもの育ちを支える仲間を支援するための取り組みを実施しました。
スカンポ募金は、募集期間を定めて周知を行ってきましたが、近年の災害の状況からご寄付のお問い合わせを継続的にいただいています。そうした状況をふまえ、年間をとおしてスカンポ募金の口座にお振込みいただけるようにしています。
いまだなお、支援を必要とする被災地への支援や今後の災害に備えるという観点から募金の周知・ご協力をお願いいたします。
なお、都道府県・指定都市別の送金件数、送金金額等の集計を行う予定はございませんので、予めご了解のほどお願いいたします。
【送金口座】
-
●三井住友銀行
東京公務部 普通預金
口座番号:168334
口座名義:全国保育士会被災地支援スカンポ募金
(ゼンコクホイクシカイ ヒサイチシエンスカンポボキン) -
●ゆうちょ銀行
郵便局からお振込みいただく場合
東京 00120-3-387991
口座名義:全国保育士会被災地支援スカンポ募金
(ゼンコクホイクシカイ ヒサイチシエンスカンポボキン)
※ゆうちょ銀行ATMの記号番号入力にてお振込みいただく際は、
「記号」は上6ケタ「00120-3」の数字、「番号」を下6ケタ「387991」の数字をご入力ください。 -
●銀行からお振込みいただく場合
支店名:019(ゼロイチキュウ)店 当座預金
口座番号:0387991
口座名義:全国保育士会被災地支援スカンポ募金
(ゼンコクホイクシカイ ヒサイチシエンスカンポボキン)
令和6年度における取り組み
令和6年度に発生した災害等に際し、当該地域の都道府県・指定都市保育士会組織に対して、状況の確認を行ったが、大きな被害は確認されず、緊急支援金の送金はなかった。
【該当する災害】
▶令和6年7月25日からの大雨にかかる災害
▶令和6年台風第10号に伴う災害
▶低気圧と前線による大雨に伴う災害
※「内閣府ホームページ」の災害救助法に適用された災害名を表記掲載
- 〔令和6年度の助成実績〕
令和6年度は引き続き、過去の被災地に助成事業を案内している。宮城県、石川県の2県から申請があり、以下の助成を行った。 -
【助成件数】 1.「被災地における子育て支援の取り組みへの助成」 0件/ 0円 2.「保育者応援研修会助成(旧:リフレッシュ研修会助成)」 1件/270,000円 3.「研修会参加助成」 0件/ 0円 4.「1~3を除く活動助成」 0件/300,000円 総合計 570,000円
令和5年度における取り組み
令和5年度は、「令和6年能登半島地震」の影響による被害の発生を受け、被災した県・市の保育士会組織を支援するため、各県・市の会員が所属する施設等の被害状況や支援の必要性を確認し、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を石川県、富山県、新潟県の保育士会組織へそれぞれ100万円送金した。
【該当する災害】
▶令和5年6月29日からの大雨による災害
▶令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害
▶令和6年能登半島地震
令和5年度は、令和4年度に引き続き、東日本大震災被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)および平成28年熊本地震被災地保育士会(熊本県、熊本市)、平成30年7月豪雨被災地保育士会(岡山県、広島県、広島市、愛媛県)、北海道胆振東部地震被災地保育士会(北海道)、令和4年台風15号(静岡県)、令和4年8月3日からの大雨による災害(石川県)を対象に、助成事業を案内している。
令和4年度における取り組み
令和4年度は、「令和4年台風15号」「令和4年8月3日からの大雨による災害」の影響による被害の発生を受け、被災した県・市の保育士会組織を支援するため、各県・市の会員が所属する施設等の被害状況や支援の必要性を確認し、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を石川県、静岡県の保育士会組織へそれぞれ100万円送金した。
【該当する災害】
▶令和4年台風15号
▶令和4年8月3日からの大雨による災害
▶福島県沖を震源とする地震(震度6強)
令和4年度は、令和3年度に引き続き、東日本大震災被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)および平成28年熊本地震被災地保育士会(熊本県、熊本市)、平成30年7月豪雨被災地保育士会(岡山県、広島県、広島市、愛媛県)、北海道胆振東部地震被災地保育士会(北海道)を対象に、助成事業を案内した(助成実績はなし)。
令和3年度における取り組み
令和3年度に発生した地震等の発生に際し、当該地域の都道府県・指定都市保育士会組織に対して状況の確認を行ったが、大きな被害は確認されなかった。
【該当する災害】
▶令和3年7月1日からの大雨による災害
▶台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害
▶令和3年(2021年)8月の大雨
▶千葉県北西部を震源とした地震(震度5強)
▶令和4年福島県沖を震源とする地震(震度5強)
令和3年度は、令和2年度に引き続き、東日本大震災被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)および平成28年熊本地震被災地保育士会(熊本県、熊本市)、平成30年7月豪雨被災地保育士会(岡山県、広島県、広島市、愛媛県)、北海道胆振東部地震被災地保育士会(北海道)を対象に、助成事業を案内した(助成実績はなし)。
令和2年度における取り組み
令和2年度は、「令和2年7月豪雨」の影響による被害の発生を受け、被災した県・市の保育士会組織を支援するため、各県・市の会員が所属する施設等の被害状況や支援の必要性を確認し、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を熊本県の保育士会組織へ100万円送金した。
また、令和元年度に引き続き、東日本大震災被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)および平成28年熊本地震被災地保育士会(熊本県、熊本市)、平成30年7月豪雨被災地保育士会(岡山県、広島県、広島市、愛媛県)、北海道胆振東部地震被災地保育士会(北海道)を対象に、助成事業を行った。
- 〔令和2年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成件数】 1.「被災地における子育て支援の取り組みへの助成」 0件/ 0円 2.「リフレッシュ研修会助成」 1件/23,618円 3.「研修会参加助成」 0件/ 0円 4.「1~3を除く活動助成」 0件/ 0円 総合計 23,618円
令和元年度における取り組み
令和元年度は、「令和元年台風15号」「令和元年台風19号」の影響による被害の発生を受け、被災した都県・市の保育士会組織を支援するため、各都県・市の会員が所属する施設等の被害状況や支援の必要性を確認し、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を岩手県、千葉県の保育士会組織へ100万円ずつ送金した。
また、全国保育士会被災地支援スカンポ募金を原資として平成26年度より実施している助成事業の対象を拡大し、以下の組織も対象とすることとした。
- ・平成30年7月豪雨被災地保育士会(岡山県、広島県、広島市、愛媛県)
- ・北海道胆振東部地震被災地保育士会(北海道)
- 〔令和元年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県、宮城県、岡山県、広島市)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成件数】 1.「被災地における子育て支援の取り組みへの助成」 1件/118,840円 2.「リフレッシュ研修会助成」 2件/452,889円 3.「研修会参加助成」 1件/300,000円 4.「1~3を除く活動助成」 2件/360,000円 総合計 1,231,729円
平成30年度における取り組み
平成30年度は、「平成30年7月豪雨」「北海道胆振東部地震」の発災を受け、被災した県・市の保育士会組織を支援するため、「全国保育士会被災地支援スカンポ募金」を呼びかけるとともに、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を北海道、岡山県、広島県、広島市、愛媛県の保育士会組織へ100万円ずつ送金した。
また、平成29年度に引き続き、東日本大震災および平成28年熊本地震の被災地保育士会を対象に、助成事業を行った。
- 〔平成30年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県、宮城県)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成件数】 被災地における子育て支援の取り組みへの助成 1件 / 299,000円 リフレッシュ研修会助成 1件 / 202,818円 研修会参加助成 1件 / 300,000円 自由枠助成 2件 / 387,890円 総合計1,189,708円
平成29年度における取り組み
会員に東日本大震災被災地の現状を伝えるとともに、災害発生時および発生後の保育士・保育教諭の専門性を考えていただく機会としていただくため、東日本大震災の被災地における子どもの育ちおよび、被災地の保育所・認定こども園における震災後の取り組みをまとめた事例集『東日本大震災被災地における子どもの育ち事例集~災害時の保育士・保育教諭の専門性を考える~』を作成した。
事例集『東日本大震災被災地における子どもの育ち事例集~災害時の保育士・保育教諭の専門性を考える~』のダウンロードはこちら
また、平成29年度においても、平成28年度に引き続き、東日本大震災および平成28年熊本地震の被災地保育士会を対象に、助成事業を行った。
- 〔平成29年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県、宮城県)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成、提供件数】 被災地における子育て支援の取り組みへの助成 1件 / 263,706円 リフレッシュ研修会助成 1件 / 54,476円 研修会参加助成 1件 / 300,000円 自由枠助成 2件 / 381,344円 総合計999,526円
加えて、平成29年度より、全国的な利便性を考慮し、ゆうちょ銀行口座を新たに開設し、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の受け入れを開始した。
平成28年度における取り組み
平成28年度は、「平成28年度熊本地震」の発災を受け、熊本県、熊本市の保育士会組織を支援するため、「全国保育士会被災地支援スカンポ募金」を呼びかけるとともに、全国保育士会 上村初美会長が、平成28年5月8日に熊本県を訪れ、全国保育士会被災地支援スカンポ募金の支援金を熊本県、熊本市の保育士会組織へ100万円ずつ贈呈した。
また、全国の会員から多くのご寄付が寄せられていること、および被災状況の長期化をふまえ、追加での送金を実施した(熊本県保育士会組織:220万円、熊本市保育士会組織:110万円 ※会員名簿上の会員数に応じた額を送金)。
あわせて、平成26年度より実施してきた東日本大震災被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)への助成事業の対象を、平成28年熊本地震被災地保育士会(熊本県、熊本市)へも拡大し、被災地保育士会への支援を行った。
被災地の現状を踏まえ、本支援策を平成29年度も継続実施することとしている。
- 〔平成28年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成、提供件数】 リフレッシュ研修開催助成 1件 / 300,000円 自由枠助成 2件 / 235,348円 総合計535,348円
平成27年度における取り組み
平成26年度から開始した助成事業(全国保育士会被災地支援事業)について、被災地がより活用しやすい助成方策として、「自由枠助成」を追加実施した。
- 〔平成27年度の助成実績〕
被災地保育士会(岩手県、宮城県、福島県)より、次の申請があり、助成を行った。 -
【助成、提供件数】 リフレッシュ研修開催助成 2件 / 467,000円 研修会参加助成 3件 / 900,000円 被災地における子育て支援の取り組みへの助成 2件 / 481,830円 自由枠助成 2件 / 256,900円 総合計2,105,730円
平成26年度における取り組み
平成25年度に全国保育士会正副会長らが、被災された会員保育士等から伺った内容を受け、スカンポ募金を再開するとともに、その募金を基に、被災地のニーズをふまえた新たな支援策を展開した。具体的には、被災地の保育士会等が主催する、保育士等を参加対象とした保育の質向上を目的とした研修会や、保育から一時離れ心身をリフレッシュさせることを目的とした研修会の開催経費、あるいは、沿岸部の保育士等が参加しやすいよう、研修会場を県庁所在地等都市部ではなく県内のブロック毎に設定した研修会の開催経費などに助成した。
平成25年度における取り組み
震災から2年後の平成25年には、全国保育士会正副会長らが被災地を訪れ、2年経過して状況がどう変化したのか、いま必要としている支援はどのようなことなのかについて、被災された会員保育士等から話を伺った。
平成24年度における取り組み
全国保育協議会・全国保育士会は、平成24年3月2日に開催された正副会長連絡会議において、平成24年度事業としての災害への備え・対応等に関する取り組みの方向性について検討を行った。
協議結果は次の通り。
- (1)「東日本大震災被災地保育所ならびに被災職員等への支援方策の検討」として、
- 1)被災保育所への事業復旧・事業継続支援(例:金銭的支援、人的支援、制度対応的支援、他)
- 2)被災地の保育職員への支援(例:心理的ケア、被災地域内での被災職員の相談・情報交換の場の設定、等)にかかる検討をさらにすすめていくこと
- (2)「保育所での「災害への備え」と「災害時の安全・安心を確保する取り組み」」として、
- 1)東日本大震災における被災保育所の対応集約と会員等への情報提供等であり、今後も継続対応していくこと
平成23年度における取り組み
- 5月11~13日
- 御園愛子顧問(当時会長)が福島県、茨城県の被災現地調査を実施。
- 5月16日
- 委員総会(第1回)において、東日本大震災被災地保育士会支援募金(通称:スカンポ募金)の開始を上程、議決。
- 5月18日
- 児童福祉関係種別協議会会長会議(第1回)にて、上村初美会長が全国保育士会の東日本大震災対応について説明。他種別協議会と情報・意見交換。
- 6月1日
- スカンポ募金の呼びかけを開始
- 7月4日
- 上村初美会長、牧野多津子副会長、尾形由美子副会長、菅野由美委員(宮城県選出)が宮城県の被災保育所を視察、保育士から震災時の対応等について聴き取り。
- 7月5日
- 上村初美会長、牧野多津子副会長、渡辺恭子福島県保育協議会副会長(前全国保育士会常任委員)が福島県の被災保育所を視察、保育士から震災時の対応等について聴き取り。
⇒『保育士会だより』243号にて報告 - 8月4日
- 尾形由美子副会長、鈴木美岐子副会長、熊谷美枝子委員(岩手県選出)が岩手県の被災保育所を視察、保育士から震災時の対応等について聴き取り。 ⇒『保育士会だより』244号にて報告
- 8月9日
- 文書審議による第4回常任委員会において、スカンポ募金を岩手県、宮城県、福島県の各保育士会へ等分に送金することを決定。
- 8月23日
- 正副会長会議にて今後の被災地支援方策について協議。被災地の支援ニーズの把握に努める方針を確認。
- 8月24日
- 第5回常任委員会で引き続き被災地の支援活動を行っていくことを決定。スカンポ募金は、宮城県保育協議会にて実施予定の保育士を対象としたアンケート調査等による被災地の支援ニーズの状況を踏まえ、今後の活用について検討することとした。
- 9月16日
- 第4回常任委員会開催時点である8月9日現在での募金実績額(14,286,590円)を等分し、1県あたり4,762,196円を岩手県・宮城県・福島県に送金した。《第1期送金》
- 10月4日
- 正副会長会議にて、今後も継続して被災地の状況把握に努め、支援方策を検討していくことを確認。
- 10月12日
- 第6回常任委員会にて、今後も継続して被災地の状況把握に努め、支援方策を検討していくことを確認。
- 10月19日
- 委員連絡会議において、尾形由美子副会長(宮城県選出)、熊谷美枝子委員(岩手県選出)、小針和恵委員(福島県選出)から、被災地の被害状況と対応活動等について報告がされ、その後、尾形副会長からこれまでの全国保育士会としての被災地支援活動を報告し、今後も継続して被災地の状況把握に努め、支援方策を検討していくことを確認。
- 10月20日
- 第45回全国保育士会研究大会アピールにおいて、被災地の保育士を支援し、保育士の立場から保育所の子どもの安全確保に努めることをアピール。
・子どもの命を守り豊かな育ちを支えるためのアピール(平成23年度) - 11月15日
- 全社協・施設協連絡会会長会議において、鈴木美岐子副会長が全国保育士会としての東日本大震災にかかる保育士支援活動について説明。
- 11月20日
- 『保育士会だより』245号に、震災対応について考える新企画「被災地からのメッセージ」(1回目)を掲載。「この土地で生きる一人として」(福島県いわき市 大倉保育園 久保田 理香氏)
- 1月10日
- 正副会長会議にて、今後も継続して被災地の状況把握に努め、支援方策を検討していくことともに、スカンポ募金口座の募金実績額の取り扱いについて常任委員会にて検討を進めることを確認。
- 1月11日
- 第8回常任委員会にて、宮城県保育協議会保育士部会が実施した「震災に関するアンケート」暫定結果を参考に、被災地の保育士支援方策について協議。3月時点での募金実績額を被災3県に等分して送金することを議決。
- 1月20日
- 『保育士会だより』246号に、震災対応について考える企画「被災地からのメッセージ」(2回目)を掲載。「力と知恵を出し合って乗り越えた震災」(宮城県仙台市 八幡こばと園 秋林 智子氏)
- 2月20日
- 第38回全国保育士研修会において被災地からの報告を実施
【報告】「東日本大震災で保育士が果たした役割」
岩手県 堤乳幼児保育園 主任保育士 芳賀 カンナ 氏
福島県 鳥川保育園 主任保育士 佐藤 美代子 氏
宮城県 青葉保育園 / 全国保育士会 副会長 尾形 由美子 - 3月12日
- 平成23年度都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナーの実践報告「災害への対応と課題、今後の保育士会活動」において、尾形由美子(全国保育士会副会長/宮城県選出)が、東日本大震災発生から1年が経過した被災地における保育士、県保育士会のこの1年の取り組み、被災地保育士アンケート、今後求められる支援活動等について報告し、今後の保育士会としての取り組みと被災地支援を考えた。
- 3月13日
- 平成23年度第2回全国保育士会委員総会において、平成24年度事業計画について協議し、引き続き東日本大震災被災地の保育士会を支援していくことを議決した。
- 4.保育士会組織の強化
- ・東日本大震災被災地の保育士会支援を継続しておこなう。
(4) 東日本大震災被災地保育士会の支援
- 3月29日
- 第2期送金分として、その時点の募金実績額を等分して、1県あたり1,415,379円を岩手県・宮城県・福島県に送金した。
《第2期送金》
宮城県保育協議会保育士部会が実施した、被災地保育所の保育士を対象にした調査実施と、その結果を踏まえた全国保育士会の対応について
宮城県保育協議会保育士部会実施の被災保育士を対象とした支援ニーズ等に関するアンケート調査の結果が平成24年3月に得られ、震災後の保育士自身の変化として、回答のあった者861名のうち約7割が心理的な不安感を有していることが判明した。さらに、「保育士自らにも支援が必要」と感じている保育士のうち、約4割が「心のサポート」を求めていることが判明した。
そこで、全国保育士会は、平成24年1月11日に開催した第8回常任委員会にて、上記調査結果を踏まえ、被災地の保育士支援方策について協議し、第1期送金(9月16日)以降に寄せられたスカンポ募金を第2期として岩手、宮城、福島の各県保育士会に3等分し、1県あたり約141万円を平成24年3月末に送金することを決定した(再掲)。この送金は、第1期同様、被災地の保育士のために使っていただくことを条件とし、たとえば、被災地の保育士が地域ごとに集まり、被災にかかるこれまでの対応や悩み等について情報や意見の交換等ができる場を設定するための経費として活用していただくなどの例を示しつつ、送金した。
- 被災地におけるスカンポ募金の活用例
-
- 被災地の保育士が地域ごとに集まり、被災にかかるこれまでの対応や悩み等について、情報や意見の交換ができる場を設定するための経費として活用していただく。
- 県組織が中心となり、心理的な疲労が蓄積している保育士の心配ごと相談をうける相談員を被災保育所、あるいは当該保育士の集会の場に派遣するための経費として活用していただく。相談員は地域の保育士OB等とし、傾聴を基本とする。
- 各被災県保育士会が実施する研修会開催経費に充てていただく(心のサポートにかかる講義等もプログラムに含めていただく)。もしくは、被災県の保育士が研修会に参加する際の参加費・旅費を補助する経費に充てることにより保育士の研修ニーズに対応する。
被災保育士を対象とした支援ニーズ等に関するアンケート調査の結果(宮城県保育協議会保育士部会実施)
昨年(2011年)11月に同県内81か所1,000名の保育士を抽出し実施。861名からの回答を得た。
同調査結果から見てとれる一人ひとりの保育士の現況と、望まれている継続支援の内容等についてその報告の一部を以下に紹介。
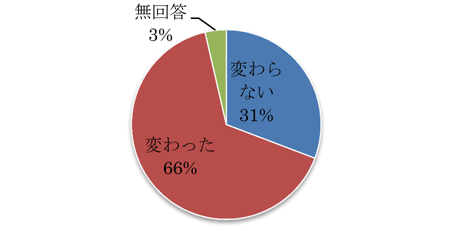
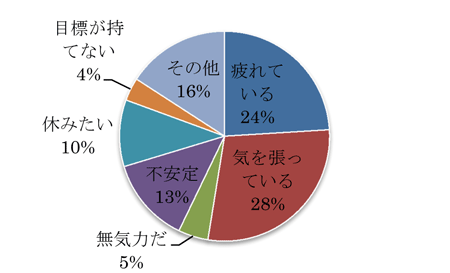
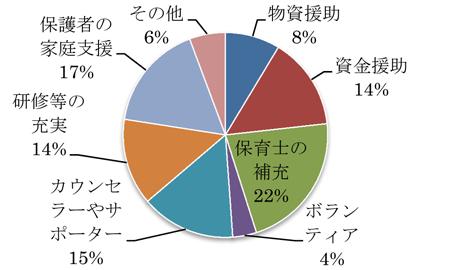
今後の「職場(保育所)への支援」については、「必要である」と回答している方が57%となっている。具体的に必要とされている支援は[グラフ3]のとおりであり、「保育士の補充」が22%と、一番高い割合を示している。
保育士の補充(確保)については、社会福祉協議会が取り組む都道府県福祉人材センター・バンク事業を通じて被災者求人情報の提供が行われてきたところであるが、本会からも必要な情報を提供するなかで、岩手・宮城・福島3県の福祉人材センターをはじめとする就職支援が行われた。
しかし、被災地の保育士不足解消のため、この課題についてはさらに継続的な対応が必要である。
また、被災された保育士の15%が「カウンセラーやサポーター」の派遣を求める、いわば「こころのケア」が必要であるとの回答をしている。本件については、厚生労働省からの申請により日本子ども家庭総合研究所(社会福祉法人恩賜財団母子愛育会)が中心となって設置された「東日本大震災中央子ども支援センター協議会」に全国社会福祉協議会が参画するなかで、被災県の保育士等を対象に行われている「子どもの福祉・保健・教育等の従事者に対する『子どもの心の理解』セミナー」開催の広報協力等を行ってきた。
一方、同アンケート結果では、「資金援助」や「研修等の充実」も14%と、高位を占めており、これらについては、被災地保育士の支援のための募金送金と、それを被災地県保育組織においてその判断により多様に活用いただくなかで対応を図ってきたところ。
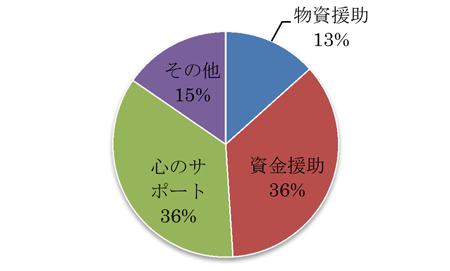
なお、アンケート調査の中では「保育士自身に必要な支援」についてもその結果がまとめられている。保育士自身の心の変化についても、最も高位なのは「心のサポート」であり、「資金援助」と同率の36%を占めている(グラフ4参照)。これに対し、宮城県保育士会では自主研修を実施し、一人ひとりの保育士を支える対応をすすめたほか、被災地の保育士が現在の状況や心境を気兼ねなく語りあえる場の設置等もすすめられた。
岩手県におけるスカンポ募金の活用
- 岩手県では、昨年度にスカンポ募金の活用方策を検討し、平成24年度と平成25年度の2か年にわたり、岩手県内の各ブロック組織に配分し、それぞれの地域の実情に応じて、保育士を支援する取り組みに活用していただくこととした。
- また、平成25年度に岩手県で開催した第47回全国保育士会研究大会では、被災した保育所跡地を視察するという震災関連プログラムを企画実施した。
福島県におけるスカンポ募金の活用
- 福島県では、平成23年度は、県内の保育の個別計画等研修会開催経費として活用したほか、会員会費免除により減少した組織運営費の補てんとした。
- 平成24年度は、平成23年度と同様に研修会開催経費、会員会費の減により見込まれる組織運営費減への補てんに活用した。
全国保育士会は、平成23年度より、事業計画の重点として東日本大震災保育士支援を掲げ、支援事業を展開してきている。
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成29年度)
(中略)
発生から1年半が経過した平成28年熊本地震や、東日本大震災等をはじめとした、大規模災害により被災された保育士等会員や被災地の子どもの育ちを守り、支援する取り組みを継続して行うことも必要です。
(中略)
- 私たちは、平成28年熊本地震や東日本大震災等、大規模自然災害の被災地保育士等をはじめとする被災地の子どもの育ちを守る会員に寄り添い、継続的に支援を実施していきます。
平成29年10月26日
第51回全国保育士会研究大会(富山大会)
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成28年度)
(中略)
本年四月には、「平成二十八年熊本地震」が発生し、多くの方が被災され、今なお困難な状況が続いています。大規模災害により被災された保育士等会員に対して、常に寄り添い、継続した支援を行って いくことが重要です。
(中略)
- 私たちは、平成二十八年熊本地震や東日本大震災等、大規模自然災害の被災地保育士等会員の取り 組みに対して常に寄り添い、継続的に支援を実施していきます。
平成28年11月17日
第50回全国保育士会研究大会
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成27年度)
(中略)
東日本大震災から四年が経過しました。時間の経過とともに、子どもや家族の状況、支援する保育士の状況も大きく変化しています。被災地の状況や支援ニーズを適時適切に捉え、今後も東日本大震災被災地の保育士を対象とした支援活動を継続的に実施していきます。
(中略)
- 私たちは、東日本大震災被災地の保育士等が現在必要としている支援内容の把握に努め、実情に即した支援活動を継続的に実施していきます。
平成27年10月21日
第49回全国保育士会研究大会
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成26年度)
(中略)
平成23年に発生した東日本大震災では、保育士たちは何よりも子どもたちの命を守ることを最優先に動きました。全国の保育所における災害発生時等の子どもの安全を確保するための対応について、保育士の視点から検討していくことが必要です。今後も引き続き東日本大震災被災地の保育士を対象とした支援活動を継続的に実施していきます。
(中略)
- 私たちは、東日本大震災被災地の保育士等が現在必要としている支援内容の把握に努め、実情に即した支援活動を継続的にすすめます。
平成26年10月16日
第48回全国保育士会研究大会
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成25年度)
(中略)
今大会は、未曾有の被害が生じた東日本大震災の被災地である岩手県において開催されます。この地で、そして各地で、保育士たちは何よりも子どもたちの命を守ることを最優先に動きました。地域によっては未だに仮園舎で保育を行っているところも少なくありません。本会では、今後も引き続き被災地の保育士を対象とした支援を継続的に実施していきます。
(中略)
- 私たちは、東日本大震災被災地の保育士等のニーズに合わせた支援活動を継続的にすすめます。
平成25年10月17日
第47回全国保育士会研究大会
子どもの豊かな育ちを支えるためのアピール(平成24年度)
(中略)
また、全国の保育所における災害発生時等の子どもの安全を確保するため、その対応について、保育士の視点から継続的に検証し備えていくことが求められています。
(中略)
- 私たちは、東日本大震災被災地の保育士等への継続した支援活動をすすめるとともに、全国の保育所において、保育士等の視点からさまざまな災害に備えた体制づくりをし、子どもの安全確保に努めます。
平成24年10月18日
第46回全国保育士会研究大会
子どもの命を守り豊かな育ちを支えるためのアピール(平成23年度)
(中略)
また、今年発生した東日本大震災に際し、私たちは、被災保育所にかかる復興に向けて継続した支援を行うとともに、全国の保育所における災害への備えと一層の安全体制の確立について取り組んでいくことが求められています。
(中略)
- 東日本大震災にかかる被災地の保育士仲間を見守り、継続した支援活動を展開するとともに、保育士の立場から、すべての地域の保育所において、常に子どもの安全確保を行うよう努めます。
平成23年10月20日
第45回全国保育士会研究大会